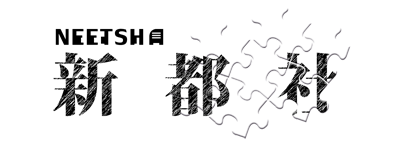街を見下ろす満天の星
2 物語に於けるヒロインの存在意義について
感染の疑惑から、二日経っても三日経っても、俺の意識は無くならなかった。再び引きこもった日の夜にはもう腹が減って、いつもの様に味気無い食事をしていた。頭がぼんやりしているのは常日頃の事だし、手足も自由に動かせる。文字もそれなりに頭に入ってくる。多分感染はしていないのだろう。最初の感染が確認されてから、一カ月が経とうとしていた或る日、電気、ガス、水道が止められた。俺は慌てた。幾らなんでも、之は生命の危機である。俺の料理には、電気薬缶で温めた水道水が要る。トイレが流せないのも不衛生だし、そもそも食材が底を尽きようとしていた。
電気が供給されなくなった為、ワールドワイドウェブに離縁を突き付けた時よりも情報が手に入り難くなっていた。家の連中の不在を良い事に活動範囲を広げた俺は、居間でテレビ番組を見ていたのに、それすら見る事が出来なくなってしまったのだ。
電池式のラジオの電源を入れた。小さな箱から陽気な声と、陰気な声が漏れ出てくる周波が一つずつあった。陽気な方は早口で何を言っているかは分からなかったが、陰気な方は、今にも死にそうな声で話している。これが私たちの使命だとか何とか。
「もしこの放送を聞いている人がいれば、連絡をください。話の通じる人が今も生存している事を望んでいます。連絡の方法は、電話番号が――。私たちは生きている限りこの放送を続けます。現在世界的なパンデミックにより、我々人類は、いや、生物は絶滅の危機に瀕しています。我々が生き残る術を――」
まるで、世界が終わったみたいな事を言っている。ほら、窓から外をのぞけば、近所の人が散歩をしているではないか。
俺は現実に目を向けた事を後悔した。近所の人の右腕は無くなっていた。シャツの袖はどどめ色に染まり、治療を施されているようには見えなかった。俺は二階にある自室に戻った。あれが歩き回っているという事が、どういう意味を持つのか分かり切っている筈の事を考察した。
政府、保安機構、そういった諸々が機能しなくなっているということだ。電気が止まったのも、ガスが止まったのも、管理できる人間がいなくなる直前に安全の為にとった処置かもしれない。もし、話が通じる状態で生きているのが、先程のラジオパーソナリティと、俺、そして俺のような引きこもりだけだとしたら……。
絶望的だ。ラジオ関係者はともかく、引きこもりの無力さを俺は誰よりも知っているつもりだ。
俺は現実を認めたくなくなった。現実を否定するために、その材料となる情報を探そうと決意した。現実を否定するために、現実に身を投じる事にしたのだ。
まず手始めとして、自宅を探検する事にした。十年以上も、自分の部屋とその向かいにある洗面所くらいしか行き来していなかったから、住んでいながらにしてまるで詳細を把握していなかった。運が良ければ両親の行先に関する手掛かりがつかめるかもしれないとも考えていた。居間に降り、使えなくなった固定電話近くに置いてあるメモ帳や、棚などを手当たり次第に調べた。両親は綺麗好きで、数日家を空けた所為で積もった埃以外は整然としていた為に、机の下に落ちていた白い長方形の扁平なメモ用紙には、屈んで直ぐに気付いた。其処には潔癖な字で、旅行で家を空ける、と簡潔に書かれていた。一体何時からだろうか。多分一週間以上は経過している。旅に出るなど呑気な事をしているという事は、初期感染者の腐敗がみられる前の事かも知れない。この爆発的な病によって、予定を大きく狂わされたのだろう。未だに家に戻っていないという事は、死んでしまったのではないか。俺のような穀潰しを文句も言わず家に置いてくれていた事に感謝はあったが、大した感慨も湧かなかった。案外そんな物なのだろう。
* * * * * * * *
今の時点では他に役に立ちそうな事は分からなかった。そこで家での探索を止め、玄関に手を掛けたが、ふと気に掛かる事を思い出した。確かではないとされていた空気感染の事例である。
現実を受け入れたくないと言っても、ウイルスを受け入れたい訳じゃない。テレビ番組では、空気感染についてそれ程取り上げていなかったから、掲示板の書き込みを当てにするしかない。情報は半月前までのものではあるが、感染力の強い病なのだとすれば、対策をしないのは馬鹿げているように思えた。
俺は部屋に戻り、コンピュータの電源を入れた。帳面型の汎用電子計算機だから、内部電源で後少しばかり使用できる。小一時間ほど、過去に読み流しした書き込みに手掛かりがないか改めて見直したものの、詳しい事は書かれていなかった。だが、ほんの数例しかなかったとはいっても、可能性は無いとは言えない。人口過密地帯で空気を介して感染したとすれば、現在の状況、ラジオで言われていた内容に信憑性が増す。俺は念の為に、湿らせたマスクをし、その上からTシャツを被り、まるで頭巾をかぶった忍者の様な格好で外へ出た。真夏の日差しの中、此の格好は酷く息苦しかった。目の前のアスファルトは空気を歪めていたが、見渡す限りでは、人っ子独り居ない様だった。
顔を隠し、でかい図体をしながら、鳥の鳴く声や物音にびくつきながらうろたえている俺を誰かが見たら、きっと言い訳の余地なく通報されることだろう。もちろん通報する人間がいればの話だが。
ところで、俺には当てがあった。隣には俺と同じ年の女の子が居るのである。幼稚園まではそこそこ遊んでいたが、小学生になってからは目も合わせてくれなくなった。俺が引きこもり始めてからも、心配して様子を見に来てくれる等という、ときめく乙女の様な事もしてくれなかった。まあ、俺にときめけというのが酷な話でもあるけれど。
兎に角、藁をも掴む、猫の手も借りたい、そんな気持ちだった俺には十分すぎる接点だった。
呼び鈴を鳴らす。軽やかな機械音が聞こえる。そういえば、意識を失った人でも、何かの間違いで呼び鈴を押す場合も在るかも知れない。そうだとすれば、唯呼び鈴を押しただけでは警戒されるかも知れない。そう思った途端に、感染者が背後に居る様な気がして振り返った。しかし、誰も居ない。念のため物影や、前後左右上下も見渡すと、彼方にアスファルト上を揺らめく人影が見えた。
噛み付かれては堪らない。さっさと調査を終わらせて、家に戻ろうと考え、意を決して大声を上げた。鏡の前で練習したとはいえ、大声は久しぶりだ。声が裏返った。
「すいませーん! 誰か居ませんか!」
途端に玄関が勢いよく開いたと思うと、俺よりも小さい人影が俺の手を引いて、中に引き入れた。物凄い力だったが、小声で叱責しているのが聞こえたので、抵抗せずに入り込んだ。
「この馬鹿っ、早く入りなさい!」
ガチャリと鍵を閉めて俺を振り返ったのは、あの時の面影を残した、もう大人に為ってしまった女の子だった。
* * * * * * * *
「あんた、何でそんな物被ってるの?」
彼女はまりという名前だ。まりはぶっきら棒に言うと睨み付けた。
「いや、空気感染すると困るから……」
太腿の半分までの丈のスカートと、真っ白なシャツを身に着けただけのまりを見て、被り物を外し、たどたどしく吃音交じりに答える。
「ふーん」
無関心の様な、馬鹿にした様な返事を返すまりに、事情を話した。
「あの、まりちゃんは無事だったんだね。結構前にパソコンが駄目に為っちゃって、ラジオでは世界が終わったような事を言っているし……」
「それで、食べ物でも無くなったの? 引きこもりのあんたでも出て来ざるを得なかったって訳?」
余りに喧嘩腰な物言いに、俺はカッと来たので黙った。まりは更に語調を強めて俺を非難した。
「あんた、馬鹿なんじゃないの? あんな大声あげたらゾンビ共が近付いて来るでしょうが!」
嗚呼、やはりそうだったのか。世界はゾンビで溢れた。あの馬鹿馬鹿しいB級の発想が、世界を終わらせてしまったのだ。
まりは、黙った儘の俺に呆れた様な溜息を吐いて、先程までの目的とは違った、情報収集のための質問をした。
「ご両親は今どうしているの?」
「えっと、旅行に出たきり戻っていないみたい。まりちゃんの……」
まりの両親について同じように聞き返そうとすると、突然破裂音が廊下に響いた。驚いた俺はまりが壁を力一杯叩いた音だと理解するのに少し時間が掛かった。暫く黙っていると、まりはゴメン、と端的に謝った。
「信じたくないんだけどね、私の両親は……」
言葉を途切らせた彼女は、何も言わず二階へと向かった。俺はアヒルの子どもの様にそれに付いて行く。
まりの両親は彼女の言うゾンビに為ってしまっていた。此処に居るという事は初期感染者では無い様だが、服で覆われていない部分を見ただけでも分かるくらい腐敗していた。鼻を衝く臭いが、二人を縛り付けて監禁している寝室の扉を開けた途端に廊下に広がる。ベッドには腐敗した体液が付けた物と思える黒い染みが、二人を囲う様に着いていた。その中で蠢く感染者が二人。俺は見覚えのある二人が口に出すのも悍ましい状態に為っているのを目の当たりにして、言葉を出せずにいた。まりは、身体を震わせながら俯き気味に言う。
「私の鼻がおかしいんじゃないよね。目がおかしくなって、お父さんとお母さんが腐っている様に見える訳じゃないよね。間違って縛り付けちゃって、私が殺してしまった訳じゃ無いよね。私が――」
俺は何も分からなくなって、彼女を抱きしめた。随分人と接していなかった所為で、こんな時に何て言っていいのか、どうして良いのか分からなくなってしまっていた。
直ぐにゴメン、と言って彼女を離したが、彼女は俺に縋り付いて泣き崩れた。脳を麻痺させていた衝撃が和らぎ、優しかった彼女の両親の記憶が、涙腺を緩ませ、鼻が詰るのを感じた。彼女の背中に手を置き、暫く其の儘にしていた。
彼女は泣き止むと、先程のピリピリした様子とは打って変わっていた。悲しげな微笑と共に、口を動かす。
「ごめんなさい。一週間以上も話の通じる人と会っていなくて、弱気になっちゃって」
先刻の悪態が強がりだったと気付き、何となくカッと来た事が恥ずかしく思えた。
「おじさんもおばさんも、あの病に罹ってしまったんだね」
「うん……」
俺は場所を変えて彼女から話を聞く事にした。扉を閉めても異臭は微かに漂ってくる。おじさんとおばさんの呻き声が聞こえ、ごそごそと身悶えする音も聞こえる。こんな所にずっと居たなら、さぞ気が滅入った事だろう。
俺達は一階の居間に移動した。道路とは反対側で、塀に囲われて人が入ってくるのは困難な庭に面している。塀の奥には別の家の窓が見えるが暗く閉ざされている。外に出る事が躊躇われる今、手入れをする訳にも行かないのだろう、背の高い雑草に覆われていた。
「僕は、もうずっと外から情報を仕入れられなくて……」
「私もよ、先刻はごめん。引きこもっていた事を馬鹿にしたような事を言ってしまったんだけど、私も短大を卒業してから仕事が見つからなくて、ずっと家に居たの」
「そうだったんだ」
「一生懸命働いていた、お父さんとお母さんがあんな事になってしまって……。私が代わりにあの病気に……」
そんな事は無い、と俺は否定したが、結局の所自分を守る為の言葉だったかも知れない。まりは呻く様に返事をすると黙り込んだので、俺は目の前に出して貰った水を一口含んだ。
「ね、これからどうするつもりなの? ずっと此処に居ても食べ物が無くなるのは時間の問題だよ」
まりは弱々しく答える。
「そうね。うちは非常食を幾らか常備しているから、少しは食べて行けるけれど、何時かは……」
「避難所の様な所って無いのかな」
「もう無いわ。在っても人が集まる様な所に行くべきじゃない」
相変わらずの小声だが、再会した時の様な力強さを感じた。マリは続ける。
「ウチの裏に住んでいる人が塀越しに教えてくれたのよ。従来の……、地震なんかの災害マニュアルの通りに、避難所で数日過ごしていたらしいんだけど、そのうちの一人が感染していて、暴れる其の人を取り押さえる間に五人が更に噛まれた。その五人も縛り付けられた状態で昏睡状態に入ったそうよ。目覚めるまでは見なかったそうだけど、其れを見ていた殆どの人は思ったわ、皆同じ場所に居たら却って危険だって」
「もしかしたら、他にも感染した人が居たかもね。実際話してくれた其の人も、一週間以上出て来ないからどうなったかは分からないわ」
分からないと彼女は言うが、本当は違うだろう。その人の末路は想像に難くない。
「そういえば、空気感染がどうとか言ってたわね。それにしてもあの格好は無いんじゃない?」
まりは突然笑い始める。俺は彼女が元気を取り戻したようで安心した反面、苦笑いを返すことしか出来なかった。まりは笑いを抑えながら、また話し始める。
「空気感染は無いって考えていいみたいよ。ただ、体液……ヨダレにまでウイルスが紛れ込んでいる事があるそうだから、どの道大勢の人が集まる所には行けないわ」
「そうか」
「食糧は、何時か隙を見てコンビニか何処かに行くしかないわ。まだ残っているかは疑問だけどね」
俺は聞き返した。
「鈍いわね、盗むのよ。まあお金を置いてきてもいいけれど、でもお金なんて何の意味も無くなってしまったのよ」
俺は何て言っていいか分からなかったが、どの道そうする他、手は無いだろうと考えた。俺が黙っているとまりも黙ったが、ぽつりと彼女は言った。
「いつまでそんな生活をしなければいけないのかしらね」
俺は気休めにもならない言葉しか思いつかずにいたが、構わずに希望的観測を述べた。
「病を治すワクチンが開発されるとか、そうすれば、病気になった人も治せるし」
「そうね」
まりは弱々しく微笑んだ。
* * * * * * * *
突然、ガラスと金属がぶつかり合う音が聞こえた。玄関が力強く叩かれたのだ。俺達は咄嗟に身構える。まりは俺の方を見て、先程あんな大声を出したからだと言わんばかりの視線を送ってきたが、何も言わなかった。俺は申し訳無く思ったが、声を発するより早く、まりに物音を立てない様に合図された。俺は口を噤んで、玄関のほうに視線を向けた。依然として、玄関を叩く音は続いている。
大きな音ではあったが、玄関が壊れる程では無かった。身動きも取れずに居ると、其れよりも遙かに大きい爆発音が聞こえてきた。同時に不気味なノックは止んだ。
この爆発音こそが、世界の破滅を告げる鐘だったのではないか、あれから数日が経った今でもそう思えてならない。
玄関を叩いていた感染者は、恐らく爆発の方に向かったのだろう。其れでも暫く身動きを取れない儘、頭を様々な疑問が渦巻いていた。
爆発の原因は何だろうか。連続して大小の音が鳴り響いていた。誰かがガス管でも破裂させたのだろうか。
「ぎゃあぎゃぎゃぎゃ!」
上機嫌な呻き声が家の近くを通り過ぎて行った。其れが聞こえなくなって漸く安心する事が出来、まりに目配せをして口を開いた。
「大声を出すのは控える事にするよ」
「そうしてくれると助かるわ」
斯う言う声も小声だった。
「感染した人は動く物に噛み付くという話だけど、襲われた場合はどうすればいいんだ? 何か知っているかい」
「殺すしかないわ」
余りに簡潔な説明に、間抜けの様に聞き返す。
「殺すしかないの、動きを止めるのよ」
「だって、そんな、肉体死の判断は……」
「そんな事を言っていたら私たちが感染者に為ってしまうわ。生き残りたいのなら、奴らが入って来られない所に隠れるか、奴らを殺すしかない」
俺は再び黙った。俺には反論が出来なかった。
「ゾンビ映画は見た事ある?」
「まあ、何本かは……」
「ゾンビは動きが鈍くて、頭を撃ち抜かないと倒す事が出来ない。参考に出来そうなのが、フィクション位しか無いのは癪だけど、其れしか想定出来そうに無いわね」
「そう、だね」
彼女は分かっているのだろうか。感染者たちは、動く物に見境なく噛み付き、食らう。つまり感染者同士でも食らい合うのだ。彼らはこの上なく破滅的な存在という事になる。種の存続と言う生物の目的が、遺伝子からそっくり其の儘欠落しているように、彼らは頼りなく歩き続ける。
其れに頭を撃ち抜こうにも、テレビゲームの様に拳銃が手元に有る訳でも無い。俺達は何度目かの沈黙に身を委ねた。
彼女の家の居間は、整頓されているだけでなく、埃も積もっていなかった。世界がこんな状態に為っても、慣習通りに掃除を続けていたのだろう。
そうだ、とまりは思いついた様に言った。
「あんた、もう食べ物が無いんでしょう? 電気も止まっちゃったし、冷蔵庫の中の物を早めに食べないといけないから御馳走してあげるわ」
本当は即席麺が二個ばかり残っていたが、頂けるのならそれほど嬉しい事はない。彼女が冷蔵庫と言ったので思いだしたが、俺は一種類の料理しか出来ないから歯牙にも掛けなかったが、家の冷蔵庫を確認していなかった。旅行の予定は精々二、三日だっただろうし、冷凍食品位は残っているかもしれない。
「ありがとう、頂くよ。それと家にも若しかしたら在るかも知れないから、後で持って来るよ」
「そう、多分あの爆発で、この辺の感染者は居なくなっているから、今の内なら行けるかもしれないけれど、無理はしなくていいわ」
結局、電気が止まっているから、駄目に為る前に持って来ようという事になり、保冷箱に冷蔵庫にあった物を入るだけ詰めて、まりの家に移動した。今は隣同士が余りにも遠い。
その晩は、久し振りに豪勢な晩飯を食べる事が出来た。ずっと同じような物しか食べていなかった俺は、一口食べるごとに美味しい、美味しいと言って食べていたから、彼女は煩く感じたかも知れない。まり自身は、良かったわ、と言うと言葉少なに食べた。
偶の外食にはしゃぐ子供の様な俺に、彼女は呆れたように言う。
「あんたは気楽そうで良いわね」
之から食事が保障されなくなる事を考えると、どれだけ楽しんでも足らないような気がしていた。一応保存の効く食品等はまだ有るが、何時まで持つか分からない。
「もう暗くなってしまったから、今日は私の家で寝なさい。変なことしたら承知しないわよ」
釘を刺されてしまったが、正直な所、今日は久し振りに外に出た上に、人と話したので、随分疲れが溜っていた。腹も十分膨れているし、ぐっすり眠れそうだ。
「じゃあ僕はソファを借りるよ」
「布団は何枚使う?」
* * * * * * * *
斯うして俺とまりの生活は始まった。まりにしてみれば選択肢が無かったというだけの事だろうから、気の毒と言えば気の毒なのだが、俺は幸運だったと言うべきだろう。世界が破滅した事を除いて。
俺は世界が崩壊したという事を、甘く見ているのかも知れない。実際まりとは、生活を一緒にする事になるというだけで、それ以上の進展は望めそうにないし、彼女と手を取りながら数々の苦難を乗り越えるという事が、俺が失ったものに釣り合うと言えるのだろうか。
どうにか物事を前向きに捉えようとしても、崩れ去った日常が其れを遮る。今正気を保っている人々が皆、選択肢を剥奪され、生きるか死ぬかの局面に追い遣られている。自ら死ぬか、何を投げ打ってでも生き残るか。常に究極の選択に晒されているのである。
結局、夜が恐ろしいと言うので、まりが眠るベッドの隣に布団を敷いて貰って寝ている俺は思う。まりが望まないのなら、俺は優しいだけの男になろう。恐怖をその隣で少しでも和らげてあげられる様に。俺はまりにとって、選択肢の中にあれば選ばれないが、無いよりは有った方が良いというだけの存在だ。しかし、其れでも良い、と思った。自分を卑下するのは得意だから。
物語に於けるヒロインの存在意義について fin PAGE TOP