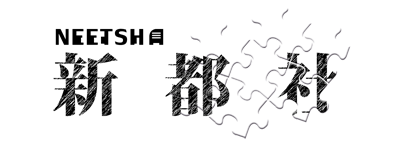街を見下ろす満天の星
3 感染者の死について
まりの両親を殺すことにした。俺がまりと再会して、三日目の事だった。結局あれから俺は自分の家に帰っていない。ノートパソコンはとうとう電源が切れてしまったし、食材も食べられる物は全て移動した。今の所危険を冒してまで戻る理由が見つからない、というのが表向きの理由だ。
その日まで両親について再び話題に出すような事はしていなかったが、まりは意を決したように切り出した。
「お父さんとお母さんを、楽にしてあげようと思うの」
茹だる様な暑さが、過去の物となった文明を嘲笑うかの様に、まりの家に侵入して来ていた。俺は為るべく薄着をしていたが、汗を掻きやすい腋や額など関係無しにじっとりとした感触が全身を包んでいた。自分でも分かる位の臭いが纏わり付いているものの、着替えも、汗を流す水すらも貴重と来ているから、お互い口に出さない様にしていた。
彼女の申し出に、俺は不思議と驚かなかった。寧ろそうして然るべきだとさえ思った。そして俺が心配したのは其の方法だった。
「今の儘では気の毒だものね。でもどうやって?」
安楽死の方法が模索され始めた所までは情報があったが、肝心の方法は分からず仕舞いだった。
「首を切り落とす、とか?」
彼女自身も分かっていないようだった。例によって、映画の設定を参考にした対処しか思いつかない。拳銃が無い以上、首を切り落とすというのが現実的だろうか。だが、遺体を損壊するという事は、見た目以上に大変なことだ。屠畜か何かを取り扱った動画を見たことがある。現実の問題に直面し、社会復帰の為と嘯いた筋肉増強訓練は、根性無しが自己満足のために気まぐれに行った程度のものであることは自明で、とても自信が持てる様なものではなく、結局のところ万年運動不足の俺と、華奢なまりの二人でどうにか為るものとは思えなかった。そして、通常の観念で言えば、遺体損壊は死者を辱める行為として蔑まれるべき行為でもある。その上肉親なのだから、彼女は果たしてその身の毛も弥立つ様な行為に耐える事が出来るのだろうか。
どのような手段を採るのか、という質問にあっけらかんと答えた彼女だが、また無理をしているのではないかという疑問が首を擡げた。そしてそう質問しかけたが、思い留まった。
仮に彼女が無理をしているとして、両親を活動停止に追い込む事を、止めさせるべきだろうか。今も二人は二階で体液を流出させながら、何重も巻かれた縄の中でもがいている。快復の希望がない事は分かり切っているにも拘らず、彼女が数日、否、俺と会う前から迷い抜いてしたのだろう決断を、安易に思い止めさせていいのだろうか。
俺は彼女の判断を信じる事にした。
「本当に首を切り落とせば、動きを止められるのかな」
額の汗を拭い、シャツに擦り付ける。雨でも降れば、二階のベランダでシャワーを浴び、バケツに水を溜める事も出来るのに。もう一週間以上真夏日が続いている。恐らく最も悪い時季に水道が止められたと言っていいだろう。歩いて行ける距離に川があっても、外に出られない今は桃源郷の様なものだ。文字通り湯水のように使えていた清潔な水が、今や貴金属に勝る価値を持っていた。
俺の率直な疑問が、彼女にとっても未知の領域だという事は勿論分かっていたが、聴かずには居られなかった。彼女は概ね予想通りの答えを言う。
「さあ、やってみなくちゃ分からないわ」
安楽死の定番と言えば毒物の投与だが、家庭にそれ程強力な化学薬品も、血管に注射する為の器材も無い。他に方法も思い浮かばなかった為、俺達は先ず母親の方を風呂場まで引き擦り込んだ。二階から風呂場のある一階まで降ろすだけでも相当に難儀した。猿轡を嵌め、手足も確り縛ってあるから、もぞもぞと動く芋虫の様だった。うっかり噛み付かれても大丈夫なように、長袖を着こみ、手袋を厳重に嵌めた。真夏、安易に換気も出来ない室内で、電気が止まり扇風機すらも動かせない状況に、最適な格好だった。
道具は包丁、日曜大工で使っていたのだろう鋸、それと首を置く台は、浴室にあった椅子を使った。俺がおばさんの身体を馬乗りになって動けない様にし、まりが後頭部を抑え付けながら、慎重に包丁を挿入していった。最初は力仕事に為るだろうから俺が代わると言ったのだが、まりは聞かなかった。
「私がやるわ。私の両親ですもの」
* * * * * * * *
腐り開いた穴から漏れ出していた所為か、思ったよりも血は噴出しなかった。おばさんはうぐうぐと呻いているが、身体をくねらせた時に偶然空気が漏れ出たような声でしかなかった。腱か骨に引っ掛かったと見えて、まりの手が止まった。包丁を、風呂桶を覆っている蓋の上に慎重に載せて、鋸を手に取った。そして、ぎこっぎこっと慣れない手つきで取っ手を前後に動かしていく。半分も刃は通っていなかったが、汗が滝のように噴き出していた。俺は、近くに在った手拭いを彼女の額に宛がった。まるで手術中の医師と看護師だな、と思ったが口には出さなかった。まだおばさんは身体をくねらせている。
午後の日差しは、その日の最高気温を叩き出し、俺達の脳髄を茹で上げんばかりだった。遠い日の記憶が蘇る様だ。もう十年も冷房器具の無い場所になど行っていない。小学生の頃は、暑さの一つや二つ、物ともせずに外で遊んでいた。辛い記憶ばかりでは無い。外へ出なくなった日々を悔いる事はあるが、其れまでは仲が良かった連中も大勢いた。俺の所為だ。ほんの一寸の事で崩れ去る人付き合いという奴が恐くなって、俺が逃げ出したから、何か確執めいたモノが俺と友人だった奴らとの間にある様な雰囲気になってしまった。それすらも俺の錯覚かもしれないというのに。もはや取り返せるものではない。
まりは、鋸が上手く扱えず難儀していた。骨の半分も刃が食い込んでいない様に見えた。
「代ろうか」
俺の言葉が聞こえないのか、返事するまでも無いと思ったのか、ずっと彼女は没頭していた。涙一つ見せないのは、余りの現実感の無さに、神経が麻痺しているのだろう。一時間も経って漸く、骨を切り離す事が出来、後は残りの肉を包丁で切り離すだけだと思った。屹度まりもそう思ったに違いない。しかし、俺達は甘かった。
「どうして!? 首は完全に切り離したのに、身体がまだ動いているわ」
頭部の動きは流石に鈍っていたが、身体は前と変わらず活発に動き続けていた。
「もしかすると、切り離してから少し時間が掛かるのかもしれない。少し待って様子を見よう」
ところが、十分経っても一時間経っても動きが止む気配はない。夕日が差し込み始めても依然として動き続けていた。
「一体どういう事なの?」
映画やテレビゲームでなくとも、尋常に考えて首を切り離された人間が動き続ける道理は無い。彼女も俺も、混乱し始めていた。
「分からない。頭が弱点じゃないのかも」
「そんな……」
二時間以上もの責め苦が唯の徒労だったと知った彼女は、風呂場から出て、薄暗い廊下に崩れ落ちた。首無しで動く彼女の母親を見て、俺は一つの連想を抱いていた。口に出す事は憚られたが、まるで頭を切り落とされても餓死するまで動き続けるごきぶりの様じゃないか。しかも、この患者達は、食事を摂らなくても一カ月以上生き続けているのではないだろうか。もし餓死しないとなると、二人を楽にする方法はあるのだろうか。
「百六十五分割……」
唐突に彼女が呟いた。筋肉少女帯というバンドのボーカルが書いた小説にもゾンビの少女達が出て来て、彼女達を活動不能に追い込むには、百六十五分割してやらなければならなかった。まさか彼女が其れを知っているとは思ってもみなかったが、しかし、やはり問題はある。
「チェーンソーでも有るの?」
彼女は驚いた表情をした。そして、首を横に振った。
「あんたもステーシーを知っていたとはね」
俺は、まあね、とだけ言うと考え込んだ。他に方法は無いだろうか。先程は否定した毒物だが、注射器が無くとも傷口に流し込めば全身に回るかも知れない。後はゾンビではないが、不死者という点でドラキュラと関連付ければ、心臓を杭で一突きにすれば或いは……。
「毒を試そうか。安楽死の方法の定番でもあるし、洗剤か何かを流し込むのも一つの手だと思う」
彼女は頷くと、浴室用の洗剤を手に取った。混ぜるな危険と書いてあるから、屹度毒物としては強烈な威力を発揮するだろう。洗剤の容器を首に宛がい、流し込む。血液が流れ落ち切っていない所為か、血管には侵入せず、食道に流れ込んでいった。するとものの数分で効果が現れ始めた。先程までとは明らかに違う、痙攣する様な動きを見せたのだが、俺達はまた失望した。陽が落ちても未だ薄明りが残る浴室で、再び同じ様に蠢き出したのである。
まりは憔悴しきって、今日は此れ以上の続行は不可能に思われた。
* * * * * * * *
「もう、明日にしよう。これ以上暗く為ったら危険だ」
彼女の眼に光が篭る。彼女は眉根を寄せて唇を噛み締めると、もう一度だけ、と言った。
もう一度と言っても、一般の家庭に塩素系漂白剤よりも危険な物が在るだろうか。俺は其の時、電撃が走った様な閃きを覚えた。
グルタミン酸ナトリウム。
俺は血を入念に洗い流し、台所へ向かった。そうして患者の体液を持ち込まない様に配慮した上で、グルタミン酸ナトリウムを含む水溶液を作った。其の効果は覿面だった。おばさんは食道に其れを流し込まれてから十分以内に先刻よりも激しく身悶えし、大きく体を捻り、終には絶命した様に動かなくなった。俺たちが取り返しのつかない道に入り込んだ瞬間でもあった。
まりが俺に緊張した視線を送って来たので、俺は唯頷いた。彼女は鈍いながら未だに動き続けている頭部にも其れを流し込み、ほっと息を吐いた。
「淋しがるかも知れないけれど、お父さんは明日にしましょう。今日は疲れたわ」
「そうだね」
新月が間近に迫る其の夜に、頼り無い明かりの下で暴れ回る感染した大男を縛り直して、グルタミン酸ナトリウムを飲ませるのは得策とは思えなかった。アウトドア用ランプの儚い暖色の光の中で汚れた衣類を一纏めにすると、食事もそこそこに床に就いた。
時計は八時半を示していた。電気が通っていない今、辺りを照らすのは途切れて終いそうな細長い月と、空を埋め尽くす星々のみだった。
俺は眠れずに居た。彼女もそうだ。疲れたと言っても、其の儘寝られる程俺達は図太くない。
「ねえ、私の事、残酷だと思う? 自分を生んでくれた親を殺して、今は柔らかいベッドに横たわっている。私って一体……」
「殺した訳じゃないよ。おばさんはもう死んでいたんだ。寧ろ楽にしてあげたと思うべきだよ」
「でも、首を切り落としたわ」
「方法が分からなかったからね。誰にでも間違いはある」
「気休めね」
「そうかもね。でも、僕がまりちゃんを残酷だと思っていないのは本当だよ」
まりは黙り込んだ。でも寝息は何時まで経っても聞こえて来なかった。
翌朝、直ぐに彼女の父親の口に例の水溶液を流し込んだ。コップ一杯でおばさんと同じ様に為った。寝室や風呂場の窓を開けておくと、臭いを嗅ぎつけたのか、カラスの大群が寄って来て此方を窺っていた。其の烏の群れに付いて来たのか感染者が五人集まって来たが、空を仰ぐばかりで手出しが出来ない様だった。驚いた事に、感染者を啄ばむなり感染者に啄ばまれるなりしているものと思っていた此の黒い小動物は、病を発症していない様だった。臭いには反応しているのに、下でうろうろしている感染者には見向きもしない。感染者は感染者で、一階の浴室から漏れ出ている筈の悪臭に見向きもしていなかった。自分から出ている同種の臭いに掻き消されているのか、臭いを感じ取る器官が腐り落ちてしまったのか、或いは両方が原因だろう。
家の前に居た五人の後ろを、両腕と両眼、そして顎が食われたのか腐り落ちたのかは分からないが、兎に角其れ等を失ってしまった巨漢が通り過ぎて行った。彼の両肩に烏がちょこんと乗って、耳を突いていた。俺達から餌を貰えないと判断したのか、此方に注意を向けていた烏達までが一斉に大男に飛び掛かり、言う甲斐の無くなった五人も其れに追従した。斯くして烏に覆われた大男と愉快な仲間達は視界から外れて行ったのである。
何故五人はお互いを貪り合わなかったのだろう。俺は考えようとしたが、止めた。おじさんとおばさんは沈黙した儘放置してあったが、俺達は昨日の疲れが癒え切っていなかった為、ぼんやりと外を眺めていた。そして、相手のくまについて何も言わずに食事を摂り、その日は終始無言で過ごした。
おじさんはかなり体格のいい人だったから、大抵の患者なら彼と同じ位の量で沈黙するだろう。現実的に考えて、感染者に襲われた場合にこの冗長な手段は何の役にも立たない事を知りながら、そんな取り留めもない事を考え、その日もまりの家で床に就いた。
俺の家は、玄関の鍵を閉めてあったし、派手な音も初日以来聞こえて来ていなかったから、屹度無事だろう。衣類が物足りなくなってきたので、明日は着替えを取りに戻ろうと思う。
感染者の死について fin PAGE TOP